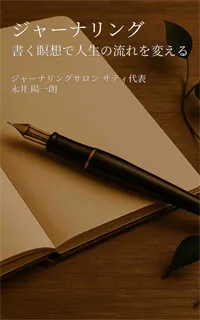永井さんの書籍を読むことをきっかけに、ジャーナリング瞑想に関心を持ちセッションを受けました。書籍内容だけでも実践するには十分なTODOが記載されていたのですが、なかなか自分の重い腰を上げることができず、セッションで初めてジャーナリング瞑想を行いました。セッション中の体験で瞑想の効果に気づくことができ、継続して実施しようと思うきっかけとなりました。特に永井さんからのフィードバックは、自身で行ったあとのジャーナリングの観察のやり方を知る上で効果的だったと思います。この度は貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。
ジャーナリングとは
ジャーナリングとは、自分の思考を文字にして可視化し、それを読み返し、客観的に観察することで自己理解を深めることのできる技法で、書く瞑想とも呼ばれています。
思考を文字化 → 思考を可視化 → 思考を客観視 → 自己理解の深まり
ジャーナリング講座のご紹介
本講座は、単にジャーナリングの実践を行うだけではありません。ジャーナリングの実践によって、紙に書き出した思考と、それを読み返して思ったことを講師に話せる範囲で話します。
その話を元に講師は、受講者に最適な「ジャーナリングのテーマ」を提案します。講師は、受講者の話に耳を傾け、自発的な気づきを促します。話の内容自体にアドバイスをしたり、意見を言ったりすることは基本的にはありません。もちろんジャーナリングについては丁寧に伝えます。
本講座では、「書き出す → 読み返す → 話す → テーマの提案 → 書き出す……」という循環を繰り返します。講座が進むにつれ、自己客観視が深まり、自分の思考や感情を客観的に、俯瞰して見る「メタ認知」が働いた状態となり、自分と思考との間に距離が生まれます(脱同一化)。
このプロセスを通じて、具体的にどのような変化が訪れるのか。次のセクションで詳しく見ていきましょう。
ジャーナリングの効果
- 自己客観視(メタ認知)
- 思考と自分との間に距離が生まれる(脱同一化)
- 思考整理
- 気持ちがスッキリする(カタルシス効果)
- 心のもやもやの解消
- 無意識の意識化
- 思考の癖、思い込みに気づく
- 自己受容が深まる
- 感謝の気持ちが育まれる
複雑に絡み合った思考を紙に書き出すことで、思考が整理されます。また、悲しみなどの感情を紙に書き出すことで、気持ちがスッキリします(カタルシス効果)。心のもやもやを紙に書き出して言語化することで、心のもやもやが輪郭を持ち、その正体が明らかになります。すると心のもやもやが解消されます。
ジャーナリングの実践によって、無自覚に巡らせている思考も紙に書き出されます。その思考を読み返し、客観視することで、無意識に巡らせている思考の癖やバイアスのかかった思考、思い込みが明らかになります。「無意識の意識化」です。実際に講座を受けた方で、「0か100か」で考える両極端な思考が明らかになった方がいます。また、思い込みに気づくことで根本的なものの見方が変わった事例もあります。
紙に書き出した思考を客観視することで、自分を責める自己批判的な思考に気づくことができます。気づくとその思考を手放し、自己受容が生まれます。
「感謝したいこと」をテーマにしてジャーナリングを実践することで、普段は意識することのない、ありがたいことにも目が向き、感謝の気持ちが育まれます。
ジャーナリングは単なる思考整理術ではありません。自分を客観的に観察することで、無意識の意識化や自己受容、自己理解の深まりへと繋がる「書く瞑想」なのです。
体験ジャーナリング講座へのお申し込み
講座に必要なもの
ノートとペンをご用意ください。
受講時間:90分間
形式 :オンライン
方式 :マンツーマン
日程 :お申込み後、メールにてご希望をお伺いし、日時を調整いたします。
講師 :永井陽一朗
料金 :4,000円
ジャーナリング講座では、人生の諸問題を解決するためのジャーナリングを伝えています。
次のセクションでは、私が、実際に行ったジャーナリング講座の事例を見てみましょう。
ジャーナリング講座の事例
パラダイムシフトが起きた
受講者のSさんは、初回のジャーナリング講座を受けた後、ジャーナリングを習慣にし、その後も何度か講座を受けていました。彼は、会社を退職し、転職活動が難航し、焦りと不安を抱えていました。しかし、ジャーナリングの実践を続けるうち、「応募先の会社に採用されなくても、どこか別の会社に採用されるだろう」と心に余裕が持てるようになったのです。彼の転職活動はうまくいき、採用が決定しました。
また、彼は、ジャーナリングの実践を続けるうち、「未来のことは予測できないため、目標設定は無意味だ」という自分の考えが、思い込みであることに気づきました。この思い込みを手放したことで、「全てのビジネスパーソンの悩みと不安を無くす」という明確なビジョン(目標)を設定することができました。「全てがヴィジョンに向かって動いている。RASが働いているのが感じられる」と、彼は力強く話してくれました。RASとは脳の機能で、人間が認識する外界の情報から、無意識のうちに自分の興味のあるものだけを拾ってフィルターにかける働きがあります。
自分の特徴に対する捉え方が変わった
受講者のSさんは、「他人の顔色をうかがい、自分の意見が言えない」という点を、自身の短所として捉えていました。しかし、ジャーナリングを通じて、それは短所ではなく、「場の観察力」であると捉え直したのです。これにより、コンプレックスだった特性が、自分独自の強みであると認識できるようになったのです。
自分の思考の癖が明らかになった
「自分には良いところが一つもない」という強い思い込みがあり、自己肯定感が低い受講者の方がいました。その背景には、0か100か、で考える極端な思考の癖がありました。「自分の良いところ」を書き出す中で、「常にではないが、状況によっては人に優しくできている」という事実を発見し、これにより、「0か100か」ではないグレーゾーンの自分を認識し、「良いところが一つもない」という考えが思い込みであったことに気づきました。これが自己肯定感を育む第一歩となったのです。
自己受容できた
ある受講者は、自己批判の声に苛まれ、精神的に相当な混乱状態にありました。講座が進むにつれ、自己客観視(メタ認知)が深まり、自己批判的な思考と自分との間に距離が生まれました。これにより、自己批判的な思考で生じていたネガティブな気分が減少し、さらには、ありのままの自分を受け入れる自己受容的な感覚が生じてきました。自らの筆記によってもたらされたその受容的な感覚に、彼は「大きなインパクト受けた」と語ってくれました。
感想レポート
MOSH
coconala
-
Oさん
-
usa yuさん
永井様
昨日はありがとうございました。先生と久々にお話でき、楽しい時間でした。
初めてジャーナリング講座を受けてから9ヶ月。ガラリと生活環境が変化したこともあり、頭の中がぐちゃぐちゃになりすぎていました。自分でジャーナリングをするのは、なかなか難しく、今回2回目の受講をさせていただきました。
自分の絡まった心が少しほぐれ、スッキリし、ポジティブ方向に思考が向いている感じがします。
またお願いいしたいと思っています。今回はありがとうございました。
講師プロフィール

永井陽一朗
ジャーナリングサロン サティ主宰
ジャーナリング講師
ヴィパッサナー瞑想協会(グリーンヒルWeb会)ボランティアスタッフ
実績:よみうりカルチャー八王子でジャーナリング講座を開講
初めまして。永井陽一朗です。私は、発達障害(自閉スペクトラム症)の特性から来る苦しみを抱えている中で、ヴィパッサナー瞑想とマインドフルネス、書く瞑想と呼ばれるジャーナリングに出会いました。ジャーナリングの実践を継続することで、心の苦しみが和らいでいく体験をし、この経験とヴィパッサナー瞑想の修行経験に基づき、ジャーナリング講師としての活動を始めました。私の内面や人生を変えたジャーナリングを苦しみを抱える人に届け、その人が苦しみから抜け出し、気持ちを楽にするために、ジャーナリング講座を開講しています。
実績・著書
実績:よみうりカルチャー八王子にてジャーナリング講座を開講
著書:「ジャーナリング 書く瞑想で人生の流れを変える」
日々生成される膨大な思考は、無自覚な反応パターンとして我々の人生を規定している。本書は、ジャーナリングを通じてこれら不可視の領域を言語化し、「メタ認知」を機能させるための技法を提唱する。
著者はヴィパッサナー瞑想の修行者として、初期仏教の「サティ(気づき)」の概念を援用し、書く行為がもたらす心理的プロセスを解明する。思考連鎖の遮断(後続切断効果)、自己批判からの解放、そして自己受容へ至る道筋を論理的に提示する点は、本書の白眉である。
内面的なパラダイムシフトは、いかにして現実の人生の「流れ」を変えるのか。「ジャーナリングサロン サティ」主宰・よみうりカルチャー講師である著者が、豊富な事例と共にその変容のダイナミズムを検証する。
真の自己理解と精神的自由を希求する読者のための、自己救済と再生の実践論。