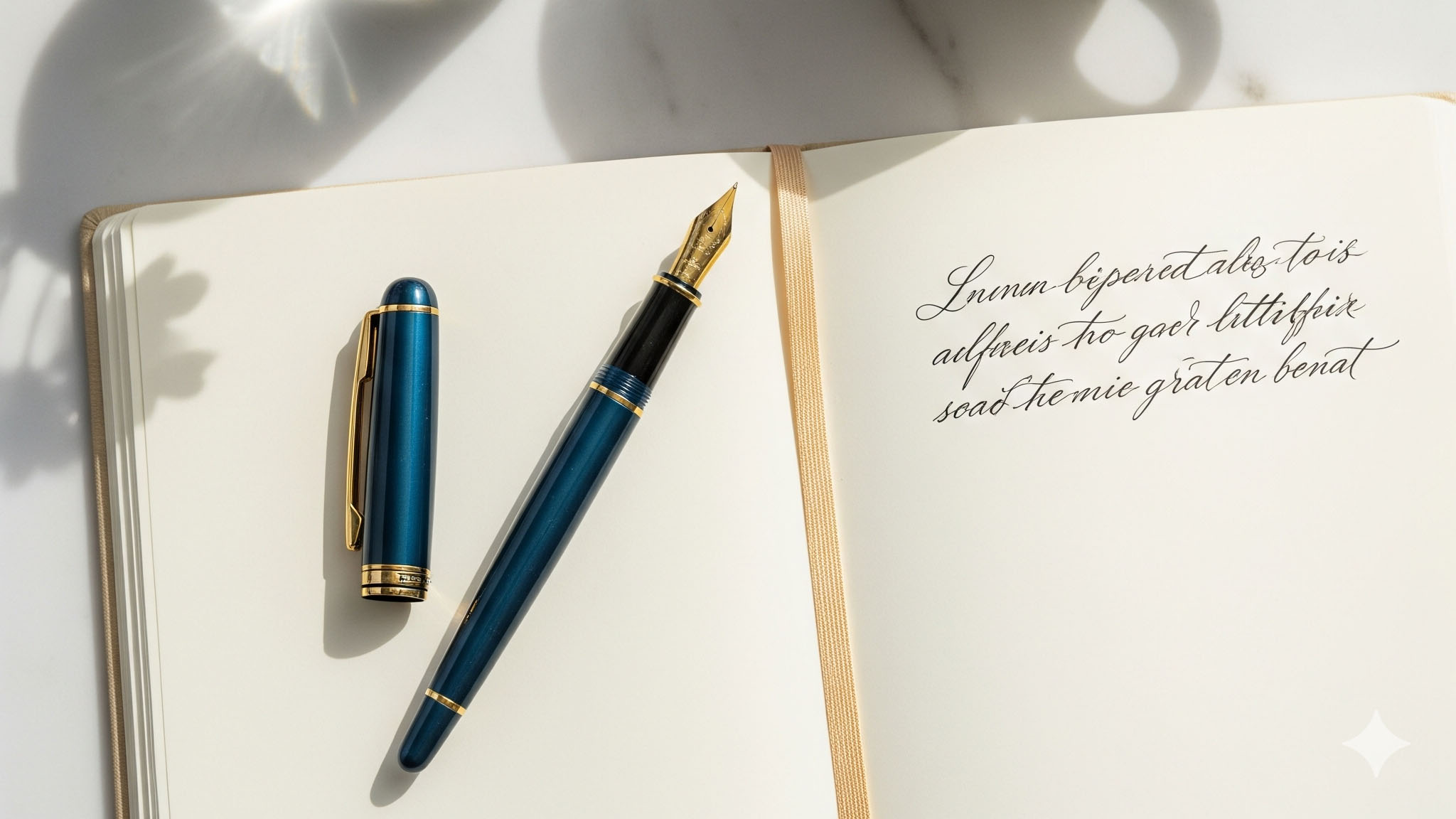事例1:転職活動における不安の解消と目標の再設定
ある受講者は、初回の対話型ジャーナリング・セッションを受けた後、ジャーナリングを習慣にし、セッションも何度か重ねていました。彼は、会社を退職し、転職活動が難航し、焦りと不安を抱えていました。しかし、ジャーナリングの実践を続けるうち、「応募先の会社に採用されなくても、どこか別の会社に採用されるだろう」と心に余裕が持てるようになったのです。彼の転職活動はうまくいき、採用が決定しました。
また、彼は、ジャーナリングの実践を続けるうち、「未来のことは予測できないため、目標設定は無意味だ」という自分の考えが、思い込みであることに気づきました。この思い込みを手放したことで、「全てのビジネスパーソンの悩みと不安を無くす」という明確なビジョン(目標)を設定することができました。「全てがヴィジョンに向かって動いている。RASが働いているのが感じられる」と、彼は力強く話してくれました。RASとは脳の機能で、人間が認識する外界の情報から、無意識のうちに自分の興味のあるものだけを拾ってフィルターにかける働きがあります。
事例2:短所と捉えていた特性の、長所への再定義
ある受講者は、「他人の顔色をうかがい、自分の意見が言えない」という点を、自身の短所として捉えていました。ジャーナリングを通じて、その行動は単なる欠点ではなく、「その場の状況を高い精度で観察する能力」であると捉え直すことができました。これにより、コンプレックスだった特性が、独自の強みであると認識できるようになったのです 。
事例3:自己批判から自己受容への移行
ある受講者は、常に内なる自己批判の声に苛まれ、精神的に「相当な混乱」状態にありました。セッションが進むにつれ、自己客観視(メタ認知)が深まり、自己批判的な思考と自分との間に距離が生まれました。これにより、自己批判的な感覚が薄れ、ありのままの自分を受け入れる自己受容的な感覚へと変化していきました。自らの筆記によってもたらされたその感覚に、彼は「大きなインパクト受けた」と語ってくれました。
事例4:「時間がない」という悩みに対する視点の転換
彼女は、介護や仕事に追われ、「時間がない」ことが悩みでした。当初、その原因を他者の協力不足など、外的要因に求めていましたが、「自分一人でも実行できる時間の作り方のアイデアを出す」というテーマでジャーナリングを行ってみたところ、「他者に頼ることには不確実性が伴う」ということに気づきました。これにより、他人軸から自分軸へと意識がシフトしました。その結果、自分自身で実行できる時間の作り方のアイデアをいくつか出すことができました。その中には現実的で実行可能なものがいくつかあり、早く実行したいいう意味のことをおっしゃっていました。
事例5:白黒思考から抜け出し、自己肯定感を育む
「自分には良いところが一つもない」という強い思い込みがあり、自己肯定感が低い受講者でした。その背景には、極端な白か黒か、で考える思考の癖がありました。「自分の良いところ」を書き出す中で、「常にではないが、状況によっては人に優しくできている」という事実を発見。これにより、「0か100か」ではないグレーゾーンの自分を認識し、「良いところが一つもない」という考えが思い込みであったことに気づきました。これが自己肯定感を育む第一歩となったのです。
事例6:「考えすぎ」の癖を自覚し、行動への一歩を踏み出す
ある受講者は、「部屋が片付かない」という悩みに対し、当初は「同居人が手伝ってくれないから」と外的要因を理由に挙げていました。本質的な原因は、物事を考えすぎてしまい、行動に移せない自身の傾向にありました。片付かない理由を書き出す中で、「考えてばかりいないで、やればいいんだ」という自身の傾向に行き着きました。これまで他者から「考えすぎだ」と指摘されても実感はなかったのですが、ジャーナリングで自分の言葉として書き出したことで初めてその自分の傾向を自覚することができたのです。
まとめ:内面の変化が、現実を変える力になる
これらの事例が示すように、ジャーナリングによって、無意識の思考の癖や思い込みを明らかにすることができます。自分自身の内面で起きる「気づき」や「視点の転換」は、気持ちを楽にしたり、具体的な行動の変化へと繋がったりします。また、時には人生の流れにも影響を与えます。「ヴィパッサナー瞑想の修行者によるマンツーマンの対話型ジャーナリング・セッション」は、講師と共に、安全な環境でご自身の内面と向き合うための時間です。書く瞑想と呼ばれるジャーナリングと対話によって、自己理解を深めていきます。